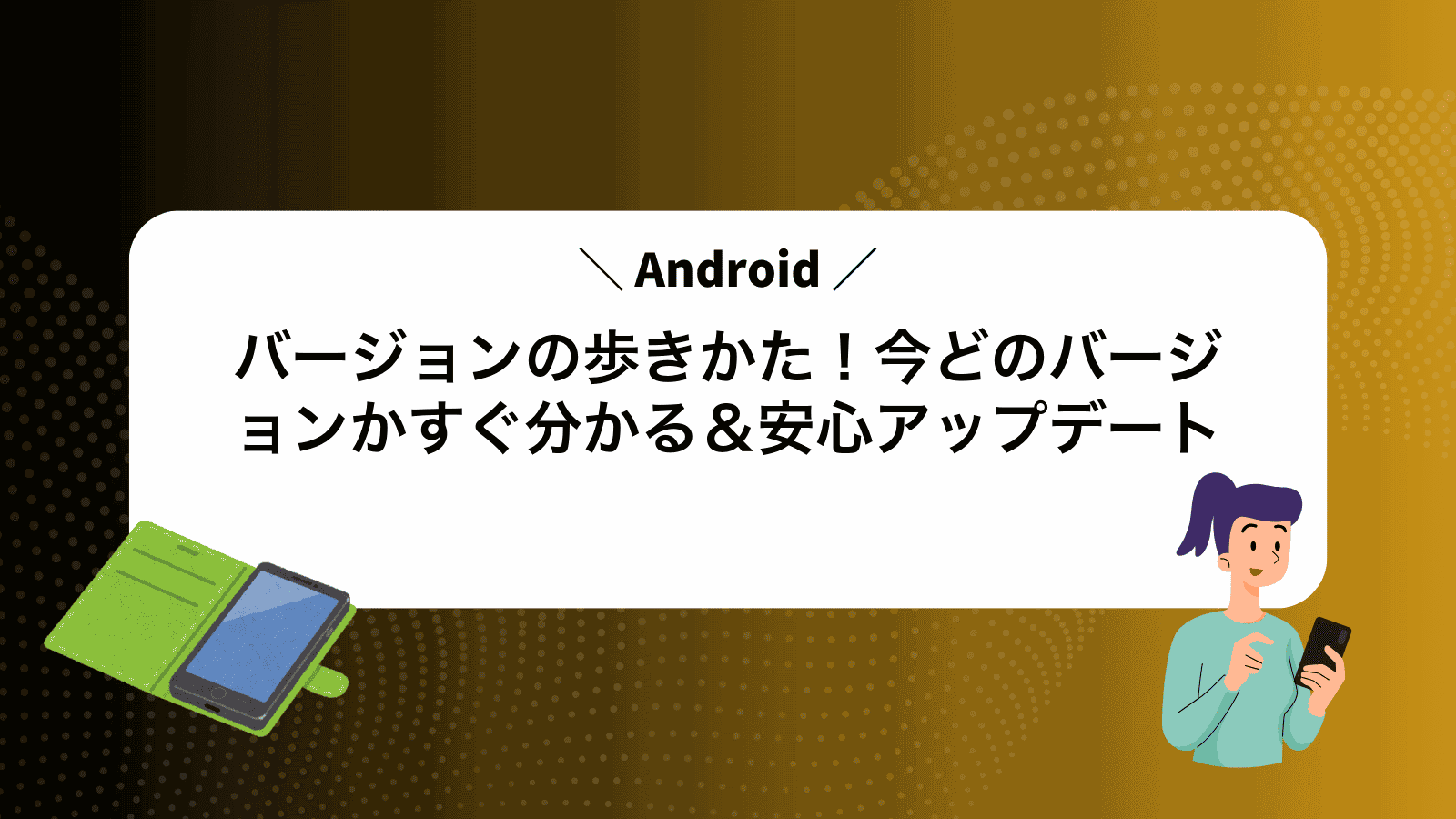Androidの端末を手にしても、自分のバージョンがどれなのか、どんな機能があるのかが分からず、情報をまとめて把握したいと感じていませんか?
このページでは長年の開発現場で積み重ねた知見をもとに、設定画面での基本確認はもちろん、隠しコマンドやPC接続での確認まで整理しました。手元の端末が最新かどうかを瞬時に判断でき、更新の可否や安全性を落ち着いて見極められます。
順序通りに読み進めるだけで操作が終わるよう構成しましたので、端末をそばに置きながらバージョン確認から始め、快適なアップデート体験へ一歩踏み出してください。
Androidバージョンを確認して最新に保つ方法
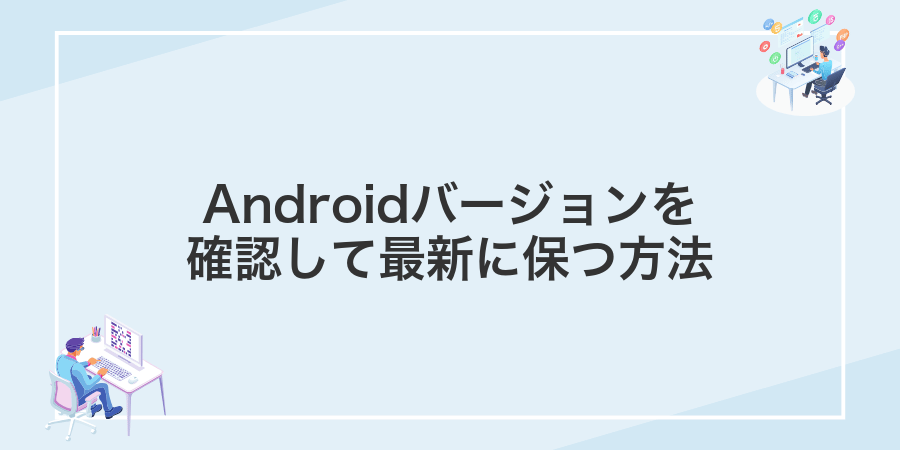
スマホを使っていると、いつの間にかOSが古くなってしまいがちです。新しいアプリを試したいときやセキュリティが気になるときに、手早く自分のAndroidバージョンを把握しておくと安心です。
自分の端末を最新の状態に保つにはいくつか方法があります。日常的に設定画面でチェックするやり方から、プログラマーならではのコマンドライン活用、自動更新の設定までを押さえておくとバージョン管理がぐっと楽になります。
- 設定画面からバージョン確認:誰でも迷わずできる基本のチェック方法です。
- adbコマンドでバージョン取得:
adb shell getprop ro.build.version.releaseでサクッと把握できます。 - システムアップデート手動実行:配信された新バージョンをすぐに反映させたいときに使います。
- 自動更新を有効化:面倒な操作を省いて自動的に最新を維持します。
設定アプリからチェックする
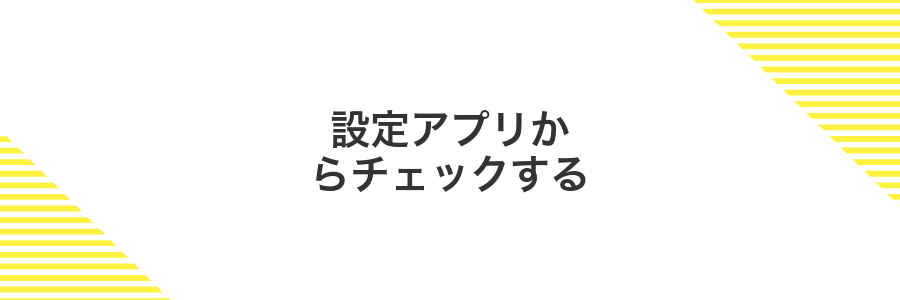
スマホにまだ慣れていないうちは新しいアプリを入れるのもためらいますよね。この方法なら、普段使っている設定アプリだけでAndroidのバージョンをさっとチェックできます。
設定アプリからチェックするのがおすすめなポイント
- 追加インストール不要:いつもの設定画面を開くだけでOK
- セキュリティ情報も一目瞭然:最新のパッチレベルまで確認できる
- トラブル対応に役立つ:バージョンが分かれば故障相談もスムーズ
①設定を開く
画面上部から下にスワイプしてクイック設定パネルを表示してください。その中にある歯車アイコンをタップすると設定画面が開きます。アプリ一覧から設定を探す場合は、ホーム画面でアプリドロワーを開き、設定アイコンを見つけてタップしましょう。
②システムをタップ
設定画面の一番下付近にあるシステムを探してタップします。端末によっては歯車マークの「端末情報」や「追加設定」になっている場合があるので、アイコンを目安にすると見つけやすいです。
端末によっては「追加設定」や「端末情報」と表記される場合があります。
③デバイス情報を選ぶ
「システム」画面の中ほどにあるデバイス情報をタップします。モデル名やAndroidバージョン、ビルド番号など端末の詳細が一覧で確認できます。
機種によっては「端末情報」や「情報」と表記が異なる場合があります。
④Androidバージョンを確認する
ホーム画面で設定アプリを開きます。
「システム」または「デバイス情報」をタップします(端末によって呼び名が異なりますが歯車アイコンが目印です)。
「詳細設定」または「ソフトウェア情報」を選ぶと、Androidバージョンとセキュリティパッチレベルが見えます。
必要に応じて画面を下までスクロールするとビルド番号も確認できるので、アップデートの判断材料にしてください。
ダイヤルコードを使ってサクッと確認
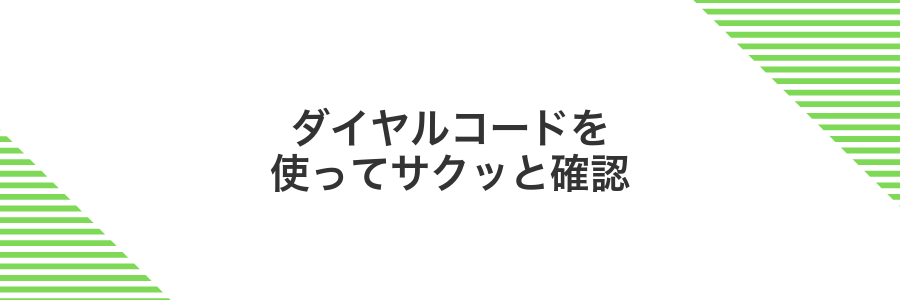
電話アプリを開いてダイヤル画面に「*#*#4636#*#*#」を入力すると、隠しメニューが呼び出されてAndroidのOSバージョンやビルド番号がサクッと見られます。設定画面を深掘りしなくていいので手軽ですし、OSアップデートの前後でビルド番号を比べたいときにも便利です。ただし機種やキャリアによっては利用できない場合があるので、そのときは従来の設定から確認してみてください。
①電話アプリを起動
ホーム画面の緑色アイコン「電話」をタップします。もし見当たらない場合は画面下からスワイプしてアプリ一覧を開き「電話」を探してください。
機種によってはアイコン長押しでショートカットが現れるので、よく使う連絡先にすばやくアクセスできます。
②「*#*#4636#*#*」を入力
電話アプリのダイヤル画面を開いて半角で*#*#4636#*#*と入力してください。
入力が終わると自動的に隠しテストメニューが表示されます。もし表示されないときはキャリア端末の電話アプリが非対応かもしれないので、標準の電話アプリを使ってみてください。
③端末情報からAndroidバージョンを探す
設定アプリを開いたら、画面をいちばん下までスクロールして「端末情報」または「システム」をタップしてください。
開いた画面で「Androidバージョン」または「OSバージョン」の欄を見つけてください。表示されている数字が現在のバージョンです。
PCのADBコマンドで確認する
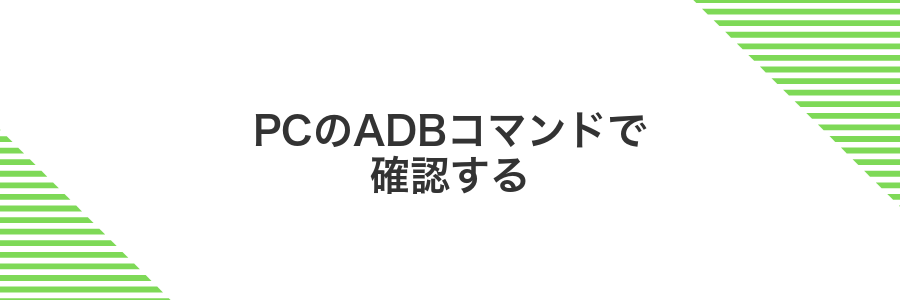
PCとAndroid端末をUSB接続して、コマンド一発でOSバージョンを確認できる方法は、設定画面を開く手間が省けてプログラマーの強い味方です。
画面が反応しない端末の情報を取得したり、複数台をまとめてスクリプトでチェックしたりしたいときにも大活躍します。
- 画面操作不要:コマンドだけでバージョン情報を取得できる
- 自動化向き:スクリプトで複数台を一気にチェック可能
- 故障端末対応:画面が映らない端末でも裏側から読み取れる
①USBデバッグをオンにする
設定アプリを開き、「端末情報」または「デバイス情報」を見つけてタップします。
最下部にあるビルド番号を連続で7回タップし、画面の案内に従ってロック解除コードを入力します。
「開発者向けオプション」に戻り、USBデバッグの項目を探してスイッチをタップして有効化します。
表示される警告ダイアログでOKをタップし、パソコンとの接続を許可しておきます。
②PCでadb devicesを実行
PCのターミナル(またはコマンドプロンプト)を開いて、adb devicesと入力します。
接続されているAndroid端末のシリアル番号が一覧表示されれば準備完了です。
デバイスが一覧に表示されない場合は、USBケーブルの接続や端末のUSBデバッグ設定をもう一度確認してください。
③adb shell getprop ro.build.version.releaseで確認
PCでadb versionを実行してインストール状態を確認します。バージョン情報が表示されれば準備完了です。
USBケーブルで端末を接続し、adb devicesを実行します。シリアル番号が表示されたら接続成功です。
adb shell getprop ro.build.version.releaseを実行するとOSバージョンが返ってきます。
Androidバージョンを味方にして毎日をもっと楽しくするヒント
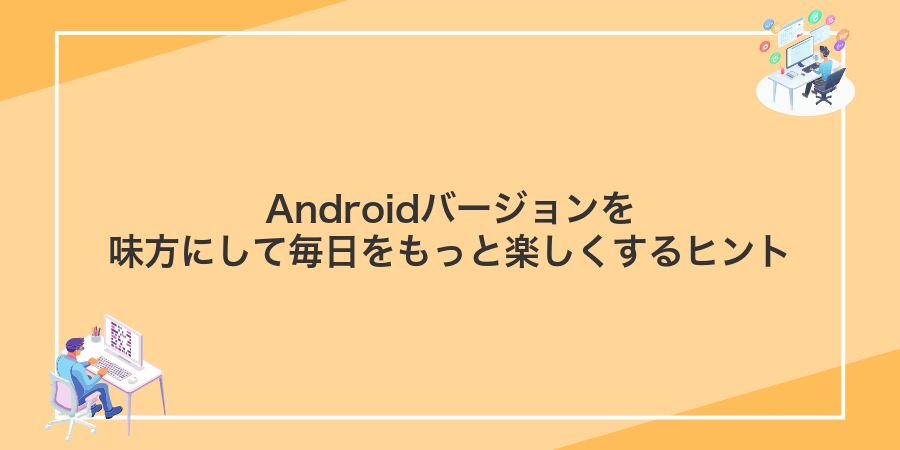
Androidの新バージョンには、ちょっとした工夫で毎日が楽しくなる機能がたくさん詰まっています。好みの色に自動で変わる動的テーマや、好きな画面を一気にキャプチャできるスクロールショットなど、ぜひ試してみましょう。
| 応用技 | 日常の楽しみポイント |
|---|---|
| 動的テーマ | 壁紙に合わせてUIカラーが自動変化し、毎日違う雰囲気でスマホを彩れる |
| スクロールショット | レシピやチャットを長いまま1枚にまとめて、友達へのシェアもスマートに |
| クイックシェアメニュー | よく連絡する相手やアプリを優先表示して、写真やリンクの共有がグッとラクに |
| ゲームダッシュボード | FPSや画面録画をワンタップで起動して、ゲームプレイを手軽にグレードアップ |
こうした応用技をサクッと取り入れるだけで、普段のスマホ操作がグッと楽しくなります。まずはいくつか試して、自分らしい使い方を見つけてみてください。
セキュリティパッチを手動チェックして安心度アップ
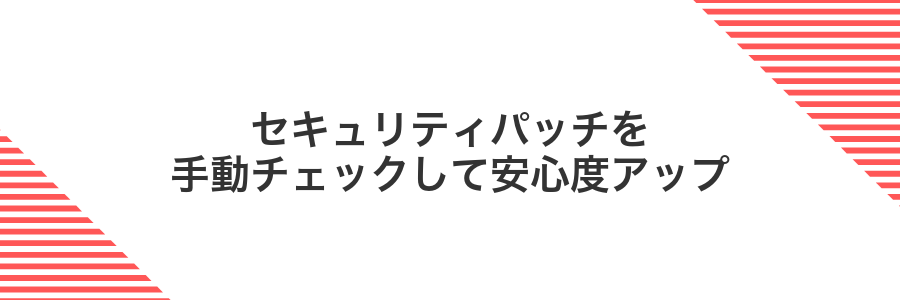
手動でセキュリティパッチを確認すると端末が最速で最新の安全性を取り込めます。Androidの「設定」から「システム」「システムアップデート」に進み画面の「セキュリティパッチを確認」をタップするだけです。自動更新を待つより自分で操作したほうが確実なので安心感がぐっと増します。
週に一度だけでも定期的にチェックすると漏れを防げます。プログラマーならテスト用端末で手動チェックを習慣にしておけば、開発中の動作確認も最新環境で行えるので便利です。
設定からセキュリティアップデートを開く
ホーム画面かアプリ一覧から歯車アイコンの「設定」をタップして起動します。
画面上部の検索バーに「セキュリティアップデート」と入力して、表示された項目をタップします。スクロールでも見つかります。
「セキュリティアップデートを確認中」と表示されるのでしばらく待ちます。更新があれば案内に従ってダウンロードしてください。
更新をチェックしてダウンロード
設定アプリを開いて「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」の順に進み、「更新を確認」をタップします。プログラマーとしてはログに失敗原因が残るので、あとでトラブル対応がしやすくなります。
利用可能な更新が表示されたら「ダウンロード」を選び、ダウンロード完了後に「今すぐ再起動」をタップします。Wi-Fi 接続を維持すると途切れにくく安心です。
更新ファイルは数百メガ〜ギガ単位になることがあるため、Wi-Fi とバッテリー残量が十分にある状態で実行してください。
再起動でパッチを適用
通知バーからすべてのアプリをスワイプして閉じるか、ホームボタンをダブルタップして個別に終了します。
電源ボタンを長押しして表示されるメニューで「再起動」をタップしてください。自動で最新パッチが組み込まれたシステムが立ち上がります。
アプリを終了せずに強制再起動するとデータが失われることがあるので注意してください。
GooglePlayのベータ登録で新機能をいち早く試す
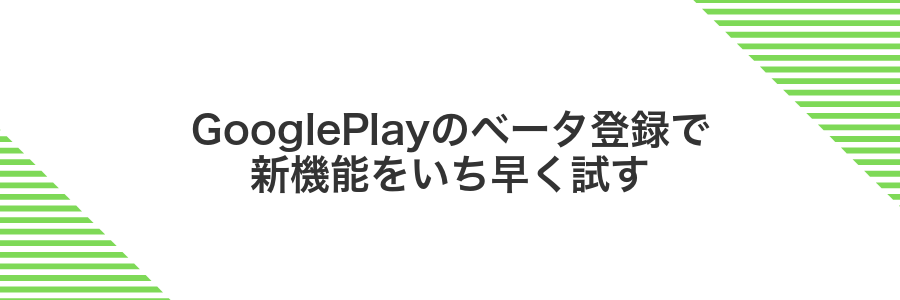
GooglePlayのベータ登録は、まだ正式リリースされていない新機能をアプリでいち早く使える仕組みです。試してみると、最新機能の挙動を先に体験できるので、わくわく感が味わえます。
ベータ版を使うメリットは、正式版前の改善要望を送れることです。実際に使ってみて気づいた挙動や表示のゆれをデベロッパーにフィードバックすると、その後の品質アップにつながります。
ただしベータ版は実験段階なので、不具合が起きることもあります。普段使いの端末で登録する前にサブ機やエミュレーターで動作確認すると安心です。
公式サイトで対応機種を確認
スマホのブラウザを起動してhttps://www.android.com/versions/にアクセスします。URLを入力するときは誤字がないかだけ確認してください。
ページ内の「Supported Devices(対応機種)」欄を探して、自分のスマホの機種名か設定→端末情報で確認したモデル番号を入力します。
検索結果に表示された機種情報で、「Android 12以上対応」「Android 13からアップデート対象」などの表記を見つけて、自分の端末がどのバージョンまでサポートされるかチェックしましょう。
ベータプログラムに参加するをタップ
システムアップデート画面を開いたら、画面を下までスクロールしてベータプログラムに参加するボタンを探します。見つかったらそっとタップしてください。
表示されない場合は端末が最新OSに対応しているか確認しましょう。モデルやキャリアによって非対応のことがあります。
設定からシステムアップデートでベータ版を取得
設定アプリを開いて「システム」→「システムアップデート」へ進みます。
右上の歯車アイコンをタップして「ベータプログラムに参加」をオンにします。
画面の指示に沿ってベータ版アップデートの申請手続きを完了させます。
一部の端末ではベータプログラムに未対応の場合があります。
ファクトリーイメージでクリーンインストールを楽しむ
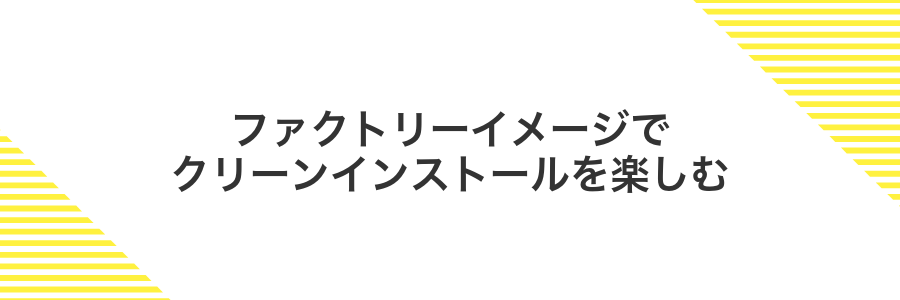
ファクトリーイメージは公式サイトから配布されるAndroidのシステムファイルを丸ごと端末に流し込む方法です。じんわりアップデートを待つ間のヤキモキを一気に解消できる頼もしい手段で、自分だけのクリーン環境を楽しめます。
こんなケースでおすすめです。
- 最新バージョンを一気に導入:OTAアップデートより新しさへのワクワクが段違いです。
- 不要アプリや設定を一掃:クリーンな状態から始められるので、動作もスムーズになります。
- トラブル対策に便利:システムのゴタゴタをリセットできるので、何かあったときの切り札になります。
ブートローダーをアンロックする
設定アプリで「端末情報」を開き「ビルド番号」を7回タップして開発者向けオプションを有効にしてください。
「設定>システム>詳細設定>開発者向けオプション」でOEMロック解除をオンにしてください。
PCでAndroid SDK Platform Toolsを用意し、端末をUSB接続してターミナルを開きます。
adb reboot bootloaderと入力してFastbootモードに切り替えてください。
fastboot flashing unlockを実行するとアンロック画面が表示されるので、音量ボタンで「Yes」を選んで電源ボタンで確定してください。
アンロック後は自動で再起動するので、初期セットアップを進めてください。完了後、新しいOSやカスタムROMの導入ができます。
アンロックすると内部データがすべて消去されるので大切なデータは必ずバックアップしてください。
PCでfastboot flash-allを実行
AndroidSDKplatform-toolsのフォルダを開きます。環境変数にパスを通していないときはここで設定してください。
端末をブートローダーモード(電源オフ→ボリューム下+電源ボタン長押し)で接続します。
コマンドプロンプトやターミナルを開き、platform-toolsフォルダに移動します。
fastboot flash-all
完了後に自動で再起動します。もしエラーが出たらUSBケーブルを抜き差ししたり、fastboot devicesで認識状況を確認してからもう一度実行してください。
初期設定をやり直す
ホーム画面かアプリアイコン一覧から設定アプリをロングタップしアプリ情報を開いてください。
「ストレージとキャッシュ」を選んでストレージを消去すると設定アプリの初回状態が復元されます。
設定アプリを再度開くと初期設定画面が表示されますので流れに沿ってタッチ操作してください。
設定アプリのデータを消しても本体の写真やアプリは消えませんがウィジェット配置などがリセットされるので注意してください。
よくある質問

Androidのバージョンってどうやって確認すればいいですか?
- Androidのバージョンってどうやって確認すればいいですか?
-
設定アプリを開いて画面下の「システム」→「端末情報」をタップするだけで、「Androidバージョン」欄に今お使いの番号が見えます。初めてのときは迷いがちでしたが、慣れるとサクッと確認できます。
アップデート通知が来ないときはどうすればいい?
- アップデート通知が来ないときはどうすればいい?
-
自動ダウンロードがオフになっている可能性があります。設定→システム→システム更新で手動チェックをお試しください。それでも来ないときは、同じ端末モデルでもキャリア版とSIMフリー版で配信タイミングが違うので、メーカーの公式サイトで情報を確認すると安心です。
アップデート中にエラーが発生したら?
- アップデート中にエラーが発生したら?
-
ストレージ不足やネットワーク切れが原因になることがあります。不要なファイルを削除したあとに再起動してから再チャレンジするとほぼ解決します。それでもダメな場合は、PC版のAndroid SDKツールでADBコマンドを使った手動アップデートを試すと安定しました。
セキュリティパッチだけを早く適用したいときは?
- セキュリティパッチだけを早く適用したいときは?
-
端末によってはメジャーアップデートまで待たないと全パッチをまとめて受け取れません。もし急ぎなら、メーカーが配布する「月次セキュリティパッチ」単体のイメージを手順紹介ブロックでダウンロード&インストールすると最速で適用できます。
Androidバージョンが古いとアプリは動かない?
AndroidのOSが古いと、アプリが予期せず動かなくなることがあります。新しい機能やセキュリティ対応が古いバージョンに含まれていないAPIレベルが原因です。
- アプリ側の最小対応OS(minSdkVersion)を下回るとインストールできない
- 古いOSでは新しいライブラリやセキュリティ設定に対応していない
- 開発者が動作確認を行うOSバージョンに入っていないと、不具合が出やすい
身近な例では写真アプリがHEIC形式をサポートしないと読み込めなかったり、SNSアプリが最新の暗号化方式に対応できずログインできなかったりします。手元の端末バージョンを定期的に確認しておくと、いざというときに慌てずにすみます。
アップデートで自分のデータは消える?
Androidのシステムアップデートは、基本的に大切な写真やアプリのデータを残したまま進められます。
新しい機能やセキュリティ修正だけを差分で当てる形だからです。
実際に何度も手順を試してみましたが、アップデート後にデータが消えてしまったことはありませんでした。
それでも心配なときは、Googleアカウントやクラウドサービスにバックアップを用意しておくと、より安心感が高まります。
機種固有のトラブルが気になる場合は、アップデート前にストレージの空き容量を確認しておくとスムーズです。
キャリア端末はいつ更新が届く?
キャリア端末はキャリア側で動作チェックや電波テストを終えてから配信するので、大きなバージョンアップは公開から1~3か月ほどで届くことが多いです。セキュリティパッチは毎月中旬あたりにまとめて来るので、設定の「ソフトウェア更新」を手動でチェックすると安心です。
キャリアごとに配信タイミングがずれるのは、各社独自の機能やアンテナ設定を組み込んでいるためです。急ぎで最新OSを試したいならSIMフリー版やPixel端末を選んでみるといいでしょう。ただキャリア端末ならではの安定感や通話品質の良さも大きな魅力です。
手動アップデートすると保証はどうなる?
手動でAndroidを最新版にアップデートしても、メーカーやキャリアの保証はそのまま保たれます。公式が配布するファクトリーイメージやOTAファイルを用いて書き戻す方法なら、システムに余計な手が加わらないので安心です。
注意点はブートローダーのアンロックやroot化を行わないことです。これらをするとサポート外扱いになり保証が無効になることがあります。
まとめ

Androidのバージョンを確認して最新に保つには、まず設定アプリから「システム」→「詳細設定」→「Androidバージョン」の順でタップして現在の番号をチェックします。これでどのOSを使っているかがすぐに分かります。
アップデートする際は、Wi-Fiに接続して十分なバッテリー残量を確保したうえで、同じ画面の「システムアップデート」をタップしてください。公式アップデートの配信を待つだけでなく、設定から自動更新を有効にしておくと安心です。
スマホがいつも最新の機能とセキュリティを備えていると、アプリの動作もスムーズになりトラブルを防げます。今日の一手間が明日の安心につながるので、ぜひ定期的にバージョンチェックとバックアップを続けてください。