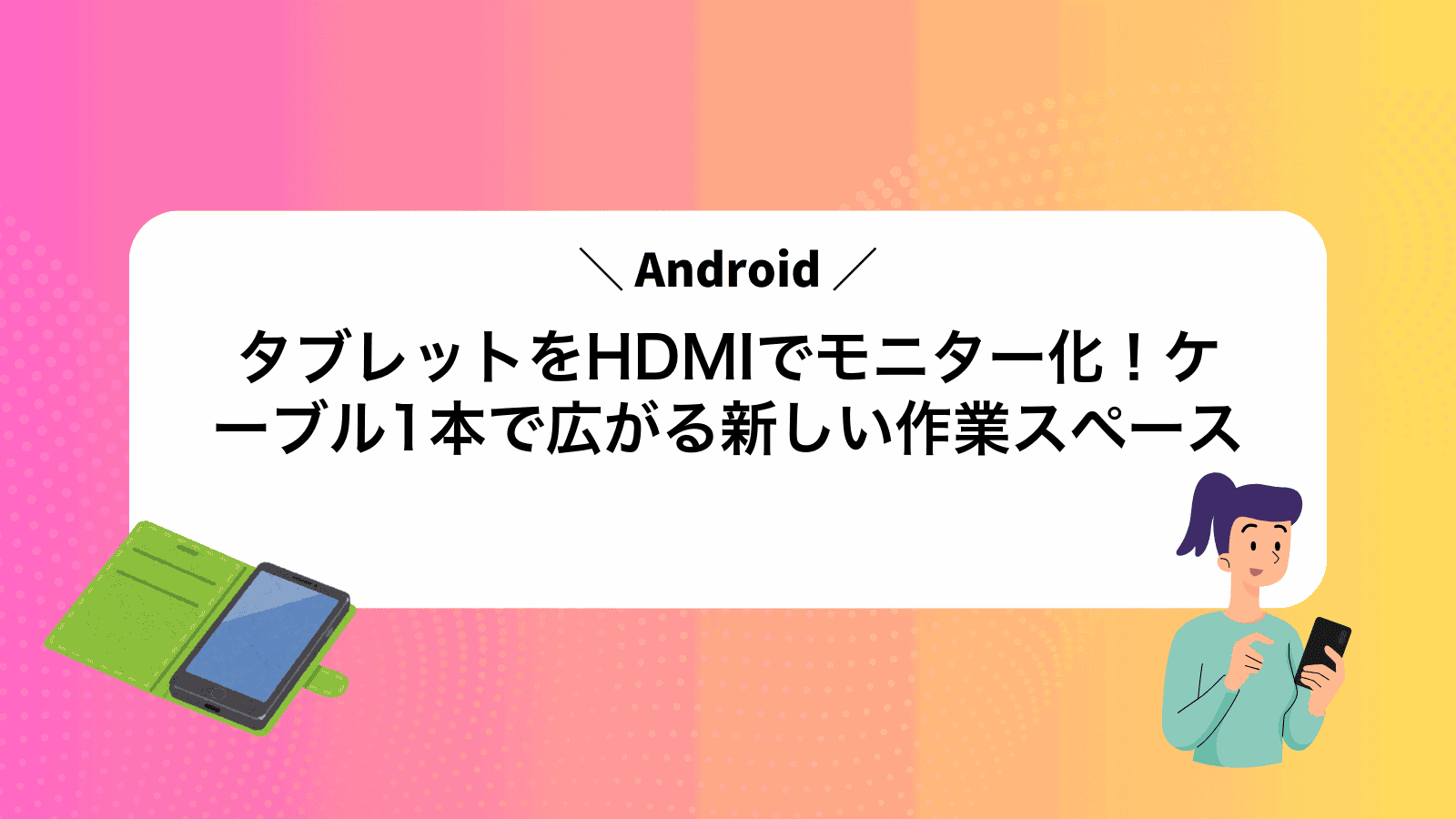外出先でも手持ちのAndroidを使ったタブレットをパソコンのサブ画面にモニター化したいのに、hdmiでどうつなげばいいのか分からず手が止まっていませんか?
ケーブル1本の物理接続と無料アプリの設定を順番に追うだけで、画面が映らない、音が出ないといったつまずきを解消できます。さらに実際に使い込む中で得たコツを添えているので、動作が安定しないときの対応まで見通せます。
順に読み進めて必要なパーツをそろえ、手元の環境で手順をなぞるだけで、外でも机の上でも映像が広がる快適な作業スペースが完成します。
AndroidタブレットをHDMIでモニター化する手順をやさしくガイド
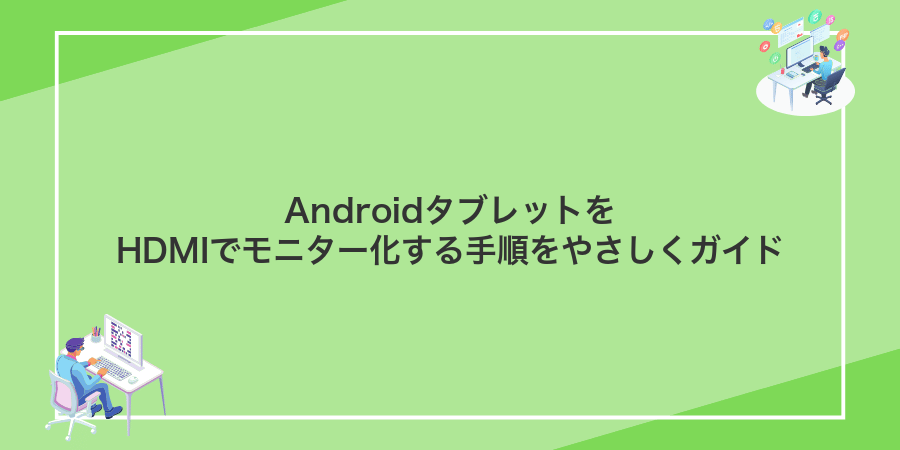
AndroidタブレットをHDMIケーブル一本でモニター化するには大きく3つの方法があります。お手持ちの端子や対応状況に合わせて選んでください。
- micro HDMI端子が内蔵されているモデル:ケーブルをそのまま挿すだけで映像出力できるので手軽です。
- USB-C to HDMI変換アダプタを使う方法:DisplayPort ALTモード対応のUSB-CポートをHDMIに変換します。
- MHL対応のmicroUSB端子を利用する方法:専用アダプタをかませることで古いタブレットでもHDMI出力が可能です。
それぞれの方法には特徴があるので、選ぶときはケーブル長や解像度対応、給電の有無なども確認しましょう。
とくにUSB-CアダプタはDisplayPort ALTモード対応かどうかを見落としがちなので、購入前に必ず仕様をチェックしてください。
どの方法を選んでも、接続後にタブレット側の画面設定で出力先を認識させるだけでOKです。次の手順で実際の接続手順を見ていきましょう。
HDMIキャプチャーアダプターを使う場合
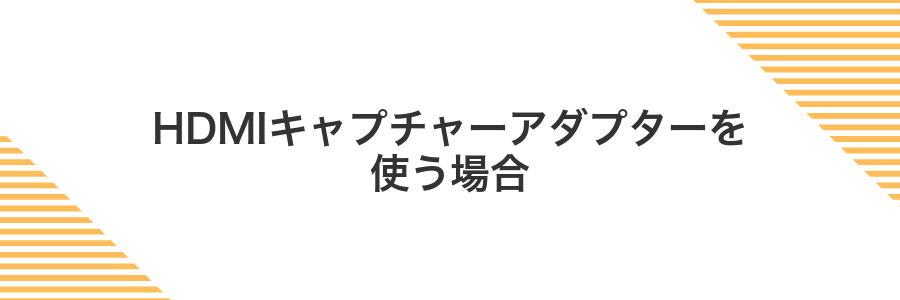
HDMIキャプチャーアダプターを使うとAndroidタブレットを有線で安定的にモニター化できます。PCのHDMI出力をUSB経由でタブレットに取り込み、遅延を抑えた映像が楽しめます。
- USBプラグ&プレイ:ドライバー不要でケーブルを挿すだけ
- 低遅延設計:ゲームや動画再生でも違和感なし
- 高解像度対応:フルHD以上もキャプチャ可能
- 安定した映像品質:Wi-Fi不要で切れにくい
特にUSB OTG対応のタブレットなら追加設定なく接続でき、プログラミング中にデバッグ画面を広く見たいときにも便利です。
①タブレットのUSB-CポートにHDMIキャプチャーアダプターを差し込む
タブレットのUSB-Cポート周辺を明るい場所で見て、向きや埃の有無をチェックしてください。
向きを合わせたら、まっすぐやさしく押し込むように差し込んでください。無理に力を入れると端子を傷めることがあります。
奥までしっかり入ると、カチッという感触がある場合があります。抜け防止になるので安心です。
②GooglePlayで表示用アプリをインストールして起動する
Android端末に画面を表示させるアプリはGooglePlayから入手できます。ここではSpacedeskを例にインストール方法を説明します。
| アプリ名 | 主な機能 |
|---|---|
| Spacedesk | Wi-Fi経由でPC画面を映し出す |
| Deskreen | 多彩なデバイスで画面共有可能 |
GooglePlayを開き、検索欄に「Spacedesk」と入力して表示されたアプリをタップし、インストールを押します。
インストール完了後に開くをタップし、ネットワークアクセスやストレージへのアクセス許可を与えます。
同じWi-Fiに接続していないとPCと端末の通信ができないので注意してください。
③パソコンのHDMI出力をアダプターのHDMI入力へ接続する
パソコン側のHDMI出力端子に合うケーブルを用意します。作業距離に合わせて長さにゆとりがあるものを選ぶと安心です。
ケーブルのコネクタを端子にまっすぐ向け、軽く押し込むように差し込みます。無理に曲げずポートを傷めないよう気をつけてください。
ケーブルの反対側をアダプターのHDMI入力端子に同じように優しく差し込みます。奥までしっかり入っているかチェックしましょう。
④アプリ設定で解像度と向きを合わせて映像を映し出す
ここでは画面共有アプリ側で外部モニターに合わせた解像度と向きを設定します。
Androidタブレットでお好みの画面共有アプリ(例:ScrCpyやAirDroid)を起動してください。
右上の歯車マークなどから設定メニューを開いてください。
接続先モニターの解像度(例:1920×1080)を選び、一覧から設定してください。
縦表示/横表示を選んで「適用」を押し、ストリーミングを開始してください。
HDMI入力対応ドッキングハブを使う場合
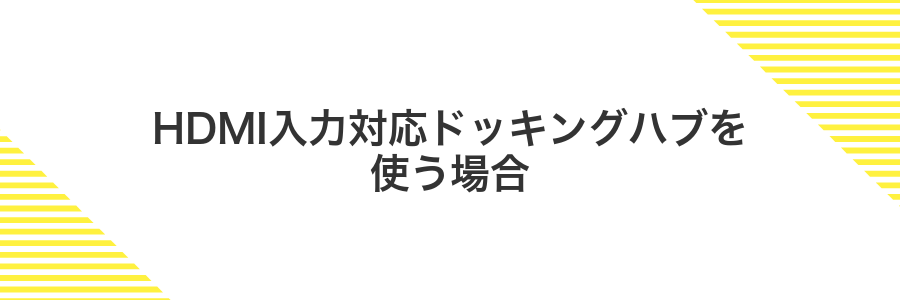
外付けのドッキングハブでHDMI入力対応のモデルを選ぶと、Androidタブレットをあっという間に大きな画面にできる方法があります。
この方法ならUSB-Cポートひとつで映像信号を受け取りながら、キーボードやマウス、さらには有線LANもまとめて接続可能です。タブレット側でDisplayPort Altモードに対応していれば、面倒な設定なしでプラグ&プレイの快適さが味わえます。
特に出先で手軽にデスク環境を作りたいときや、配線をなるべくシンプルにしたい人にはケーブル1本で完結できるこの方法がおすすめです。
①ドッキングハブをタブレットのUSB-Cポートにしっかり装着する
ハブのコネクタに傷やホコリがないことを確認してから、タブレットのUSB-Cポートにまっすぐ差し込みます。斜めにならないように真っ直ぐ押し込むと、奥まで入った感触が軽く「カチッ」と伝わります。
無理に押し込むと端子を傷めることがあるので、固いと感じたら向きを確認してから再度試してください。
②付属アプリまたは標準USBビデオクラスに切り替える
ケーブルを接続したら画面上部からゆっくりスワイプして通知パネルを開きます。
「USBを~」と書かれた設定項目をタップして、「USBビデオ機器(UVC)」または「ビデオカメラ出力」を選んでください。
付属の画面出力アプリがある場合は、そちらを起動するともっとスムーズに外部映像が立ち上がります。
③HDMIケーブルでパソコンとドッキングハブをつなぐ
まずパソコン本体のHDMI出力ポートを探します。外側にある平たい長方形の差し込み口が目印です。
差し込み口がわかったら、HDMIケーブルのコネクタを向きに注意しながらまっすぐ差し込みます。無理に押し込まないようにしましょう。
ケーブルがしっかり奥まで入ったら、軽く引っ張って抜けやすくなっていないか確認してください。
次にドッキングハブ側のHDMI入力ポートにも同様にケーブルを差し込み、両端がしっかり接続されていることを確かめます。
接続後にパソコンのディスプレイ設定を開き、外部ディスプレイが認識されているかチェックしましょう。Windowsなら「設定→システム→ディスプレイ」で確認できます。
HDMIケーブルは4K60Hz対応などの規格をチェックしておくと、高解像度でも映像がカクつかずスムーズに表示できます。
④タブレット画面に映像が出たら輝度と音量を調整する
画面上端から下へゆっくりスワイプしてクイック設定パネルを表示します。
表示されたスライダーを左右に動かして画面の明るさを好みに合わせます。
側面の音量ボタンを押すかクイック設定内の音量アイコンをタップしてスライダーを動かします。
自動輝度機能がオンだと明るさが自動で変わることがあるのでオフにしておくと安定します。
無線ミラーリングアプリで補助する場合
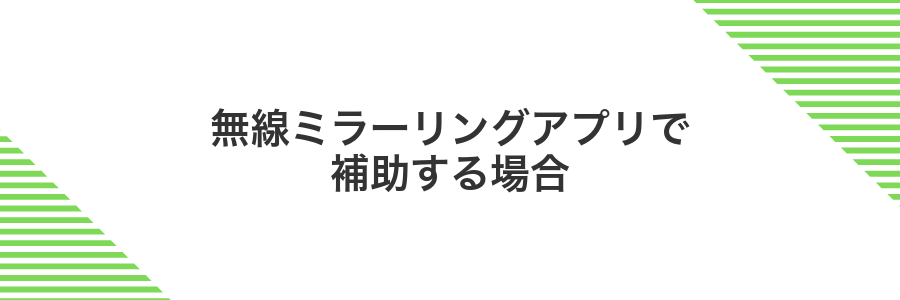
HDMIケーブルをメインに画面出力するのが安定だけど、ケーブルが短くてデスクの隅まで届かないときや、タブレットをちょっと移動しながら見せたいときに無線ミラーリングアプリが助かります。Wi-Fi経由で手軽に画面を共有できるので、長めのケーブルを用意する手間を省けるのがうれしいポイントです。ただし、無線ならではのわずかな遅延や画質の劣化は避けられないので、動画編集やゲームのようにタイムラグが気になる作業にはHDMI接続を優先すると安心です。
①同一Wi-Fiに接続して「無線で表示」系アプリをインストール
AndroidタブレットとPCを同じWi-Fiネットワークに接続します。ルーター名やパスワードを間違えないように注意してください。
Google Playから「Spacedesk」「AirScreen」「WiDi」などの無線で画面を映せるアプリを探してインストールします。遅延が少なく快適に使いたいならSpacedeskが使いやすいですよ。
②パソコンに送信用クライアントを入れて起動する
まずはパソコン側で画面を送るためのソフトを用意します。おすすめはSpaceDeskです。
1.SpaceDeskの公式サイトからWindows10/11用Serverをダウンロードする。
2.ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックして画面の指示にそって進める。
3.インストールが終わったらデスクトップ右下のタスクトレイからSpaceDesk Serverを起動する。
4.初回起動時に表示されるファイアウォールの許可ダイアログで許可をクリックする。
5.タスクトレイのアイコンが緑色になっていればサーバーが動いています。
最後にパソコンとAndroidタブレットが同じWi-Fiネットワークにつながっているか確認するとスムーズにつながります。
③アプリのペアリングコードを入力して接続する
Androidタブレットで専用アプリを起動すると画面に「ペアリングコード入力」のボタンが出ます。
ケーブルでつないだモニター側には4桁のコードが表示されるので、その数字をタブレット画面の入力欄に同じように入力してください。
入力が終わったら「接続」をタップします。成功するとモニターにタブレット画面が映り始めます。
もしコードが見当たらないときはモニターの設定画面を再読み込みすると最新のコードが出ることがあります。
モニターへの出力に遅延が気になる場合は、USB-C変換アダプターがディスプレイポート「Alt Mode」に対応しているか確認してください。
④遅延が気になるときは画質設定を下げて滑らかさを優先する
まだ有効化していないなら設定→端末情報→ビルド番号を7回タップして開発者向けオプションを用意します。
設定→システム→開発者向けオプション→シミュレートディスプレイに進みます。
720pや540pなど低解像度を選ぶと映像処理が軽くなりHDMI出力の動きが滑らかになります。
遅延が減ったことを実際に確かめてください。
元の画質に戻したいときはシミュレートディスプレイを「なし」に戻します。
モニター化できたらこんな楽しい使い方が待っている
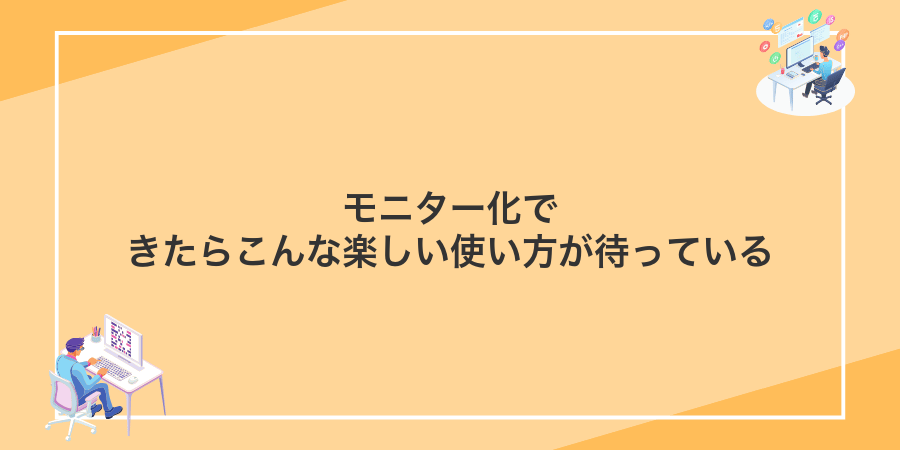
タブレットをサブモニターとして使えるようになると、手元と大画面を行き来する楽しさが増します。
| 活用例 | どう役立つか |
|---|---|
| プレゼンテーション | タブレット画面でノートを見ながら、大画面にスライドを映せるので自然な流れで進行できる |
| デュアルディスプレイ | コードや資料を大画面に、チャットや資料をタブレットに分割して作業効率がアップする |
| ゲーム実況 | タブレットでコメント欄や配信ツールを操作しつつ、大画面でゲーム画面を楽しめる |
| 映画や動画視聴 | ソファでくつろぎながら、迫力ある映像をテレビやモニターで満喫できる |
| リモート会議 | 参加者の顔を大きく映しつつ、チャットや資料をタブレットで同時に確認できる |
パソコンのサブディスプレイとして資料を並べる
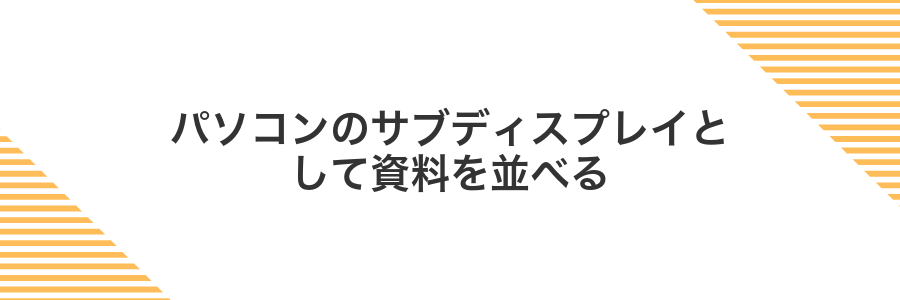
パソコンで資料を開きながら作業するときは、Androidタブレットをサブディスプレイとして活用すると画面がぐっと広がります。
対応するタブレットならUSB-Cポート経由で映像が入力できるので、HDMIケーブルとUSB-C変換アダプタをつなぐだけでパソコン画面をそのまま横に表示できます。
画面を並べることで、メイン画面で文章作成しつつサブ画面で仕様書やウェブサイトを同時にチェックできるので、資料のコピペや確認がスムーズになります。
タブレット側は自動回転をオフにして縦置き・横置きどちらでも安定した表示にしておくと、デスクまわりがすっきり使いやすくなります。
タブレットを縦置きして文書プレビュー専用にする
角度調整できる縦置きスタンドにタブレットを立てかけます。安定感が高く文書プレビューに集中できます。
画面を下から上へスワイプしてクイック設定パネルを開き、オート回転ロックをオフにします。これで縦画面をキープできます。
お好きなドキュメントビューアアプリを起動し、全画面表示に切り替えると縦画面向けレイアウトで文書が読みやすくなります。
ゲーム機の映像を取り込んでどこでもプレイ
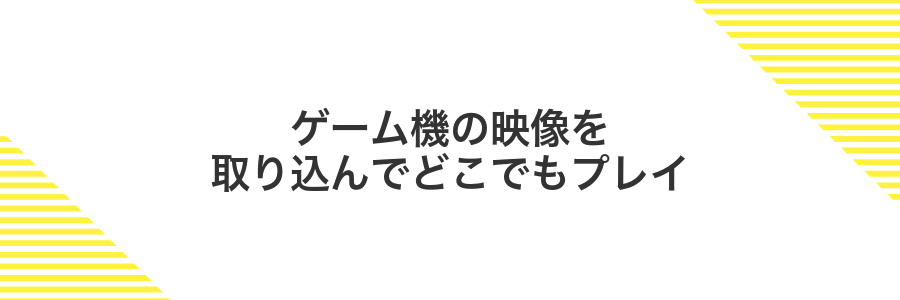
外出先でも大画面でゲームを楽しみたいときにぴったりです。HDMIキャプチャーをAndroidタブレットのUSB-Cに接続すると、PS5やNintendo Switchの映像をリアルタイムに映し出せます。お気に入りのソファやカフェのテーブルで、大型テレビのような感覚でプレイできるのが大きなメリットです。
さらに、タブレットをスタンドに立てておくと設置場所を選ばず安定して遊べますし、モバイルバッテリーでタブレットとキャプチャー機器を同時給電すれば電源の心配もありません。旅先のホテルや友達の家でも、自分だけの据え置きゲーム機のように使えるのが楽しさのポイントです。
小型スタンドに立ててSwitchやPS5の画面を楽しむ
小型スタンドを机に置き、タブレットを約60度の角度でしっかり立てかける。
SwitchやPS5のHDMIケーブルをUSB-C⇔HDMI対応アダプターに差し、タブレットのUSB-Cポートへ挿す。
タブレットが自動で映像を検出しないときは、クイック設定の外部入力からHDMIを選び、ゲーム画面が映るまで調整する。
Switchの一部モデルやPS5はHDCP制限で映らないことがあるため、映像出力対応のアダプターを選ぶと安心。
カメラのライブビューを大きく映して撮影を快適に
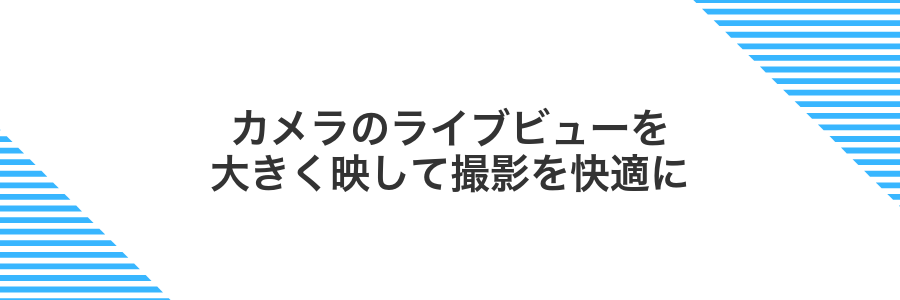
一眼レフやミラーレスのHDMI出力をAndroidタブレットで受けると、カメラ背面の小さいモニターよりずっと大きな画面でライブビューを確認できます。
大きなライブビューならピント合わせや構図チェックがグッと楽になり、友達や家族との集合写真をリモートシャッターで撮るときも、手元のタブレット画面越しに仕上がりを確認しながら快適に操作できます。
HDMI出力付きカメラとつなぎ撮影構図をチェックする
HDMI出力付きカメラとAndroidタブレットをつなげるには、USB-C対応のHDMIキャプチャアダプターと対応アプリが必須です。接続後はタブレット画面にカメラ映像が映るので、構図をリアルタイムでチェックできます。
Google Playから「USB Camera – Connect EasyCap or UVC」などの外部カメラ対応アプリをインストールし、USB-C to HDMIキャプチャアダプターを手元に用意してください。
カメラのHDMI出力端子にHDMIケーブルを差し込み、もう一方をキャプチャアダプターに接続します。ケーブルはしっかり奥まで差し込んで抜けないようにしましょう。
キャプチャアダプターのUSB-C端子をタブレットに差し込みます。初回は画面に許可ダイアログが出るので、外部USB機器を許可して映像入力を有効にしてください。
インストールした外部カメラアプリを起動し、HDMI入力を選びます。タブレットに映る映像を見ながらカメラのアングルやズームを調整して、理想の構図になるまで微調整してください。
よくある質問

- HDMIケーブルをつないでもタブレットが映らないのですがどうしたらいいですか?
タブレットのUSB-C端子が映像出力(DP Alt Mode)対応かをまず確認してください。対応していない機種だと映像が出ないことが多いです。対応機なら高品質な変換ケーブルやハブを使うと認識率がグッと上がります。
- HDMI接続中もタブレットを充電したいときはどうしたらいいですか?
USB-Cのパススルー給電対応ハブやドッキングステーションを選ぶと充電しながら映像を出せます。Ankerなどのメーカー製でPD(パワーデリバリー)対応と書かれているものを選ぶと安心です。
- HDMI接続したときに音声はモニターから出ますか?
機種によりますが多くのタブレットは映像といっしょに音声もHDMI出力できます。設定から音声出力先をHDMIに切り替えてください。音が出ない場合はタブレット側のサウンド設定を見直すと直ることがあります。
- 接続したモニターでタッチ操作や回転はできますか?
映像信号のみを出すのでモニター側でタッチ操作は反応しません。画面の向きはタブレット側の自動回転設定が有効になっていれば連動しますが、モニター自体を回転させる機能はありません。
映像が映らないときはどうすればいい?
外部出力がうまくいかない原因はケーブルや設定のすれ違いであることが多いです。まずは落ち着いて一つずつ確認しましょう。
- ケーブルと変換アダプターの接続がしっかりしているか確認。
- モニターの入力ソースをHDMI端子に合わせる。
- タブレットの電源を一度オフにしてから再起動。
- USB-C Alt Modeに対応したケーブルかチェック。
- 別のケーブルやUSB-Cポートで試してみる。
- 設定→ディスプレイ→外部モニター出力の項目を確認。
- モニターの解像度とタブレット出力の相性を調整。
注意点:すべてのAndroidタブレットが映像出力に対応しているわけではありません。メーカーサイトで対応状況を事前に確認しましょう。
音声がタブレットから出ないのはなぜ?
HDMIケーブルで外部モニターに繋いだとき、タブレット本体から音が出ないのは、音声出力先がモニターやアダプター側に切り替わっているからです。映像だけ転送する安価なケーブルやアダプターを使うと、音声信号そのものが届かず無音になります。
- HDMIケーブルや変換アダプターが音声対応していない
- 外部モニター自体にスピーカーまたは音声出力端子がない
- タブレット側の音量設定がミュートや最小になっている
- システム設定でBluetoothやヘッドホンが出力先に優先されている
まずは音量ボタンでミュートを解除し、設定画面のサウンド項目で出力先を確認してみましょう。
それでも音が出ない場合は、MHLやHDMI音声対応の変換アダプターに切り替えるか、外部スピーカーをモニターの音声出力端子に接続するとしっかり聴こえるようになります。
実際に1000円台の映像のみ対応ケーブルでは無音でしたが、2000円前後のMHL対応アダプターに変えたらタブレットの映像も音声もスムーズに出力できました。
充電しながらモニター化できますか?
市販のUSB-CハブでPD(電力供給)対応モデルを選べば充電しながら画面出力できます。私の体験では65W以上対応のハブを使うと電池残量を気にせず長時間モニターとして活用できました。ハブのPDポートに純正アダプタをつなぎ、USB-C→HDMIケーブルを差し込むだけで準備完了です。
遅延を減らすコツはありますか?
- 遅延を減らすコツはありますか?
-
有線のHDMI接続ならワイヤレスに比べて遅延がかなり抑えられます。
まずは信頼できる高品質なUSB-CtoHDMIケーブルを使いましょう。安いケーブルは信号が弱くなりやすいです。
次に開発者向けオプションで画面アニメーションをOFFにすると、表示のキビキビ感がアップします。
さらに余計なアプリを終了して処理を軽くすると、タブレットのGPUが映像出力に集中できます。
最後に省電力ではなくパフォーマンスモードに切り替えると、よりスムーズに操作できます。
おすすめのHDMIキャプチャーはありますか?
HDMIキャプチャーは種類が多くて迷いやすいですが、実際にプログラミング作業や動画配信で使ってみて「使いやすい!」と感じたモデルを紹介します。
- Elgato HD60 S+:低遅延&フルHD60fps対応で安定感抜群
- AVerMedia Live Gamer Mini:コンパクトでUSBバスパワー駆動OK、予算重視にもぴったり
- UGREEN USB 3.0 キャプチャーカード:コスパが高く、汎用性のあるシンプル設計
どれもドライバー不要のプラグ&プレイで使えて、USB3.0ポートにつなぐだけでサクッとモニター化できます。特にElgatoは負荷が軽くプログラマー作業中の動作が滑らかなのでおすすめです。
USBポートはPC背面のUSB3.0(青ポート)に接続することで安定動作をキープできます。
まとめ

HDMIケーブルと対応アダプターを用意して、AndroidタブレットのUSB-C(またはmicro-USB)端子に接続し、モニター側の入力を切り替えるだけで、ケーブル1本で大画面化ができました。
接続後は、タブレットの「ディスプレイ設定」から解像度や画面の拡張モードを調整して、新しい作業スペースをサクッと整えるだけで完了です。
家でもカフェでも、自分好みの大画面環境でコードを書いたり動画を見たり。あとはいろいろ試して、自分だけの最強デスクを楽しんでください。