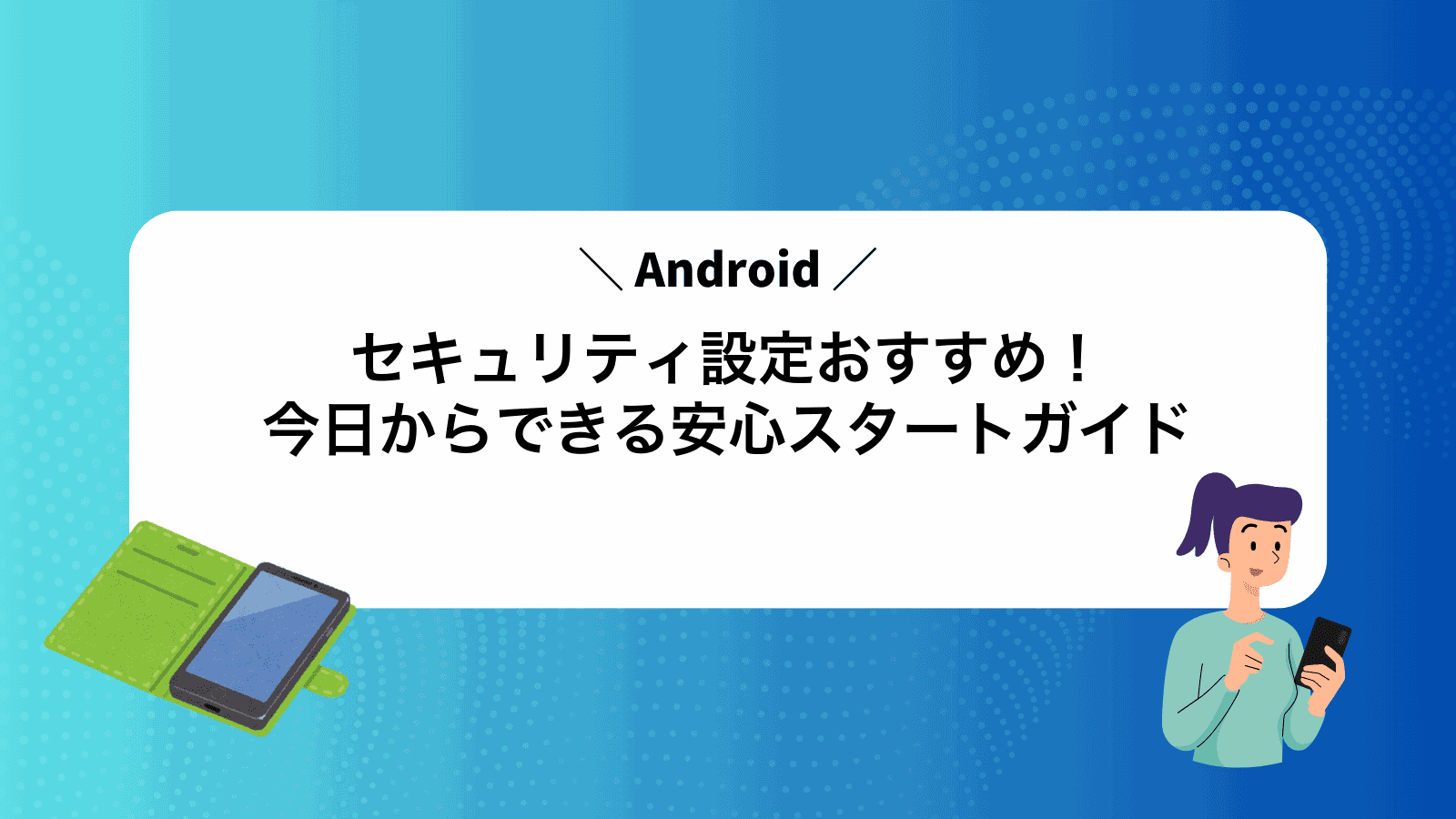新しいAndroidを手にしたものの、セキュリティを万全にする設定が多すぎて、どれがおすすめなのか迷っていませんか?
この記事では、長年Androidを扱う現場で磨かれた安全チェックリストを元に、画面ロックからGoogleアカウントの二段階認証まで、手間をかけずに要点だけを押さえる流れをまとめています。実際に端末を運用しながら検証した方法なので、迷わず安心を得られます。
まずは以下の手順を確認して、今すぐできる項目から順に試してみてください。数分で端末の守りが一段階強くなり、アプリや大切な写真を安全に保てます。
Androidのセキュリティ設定をやさしく全部まとめて行う手順
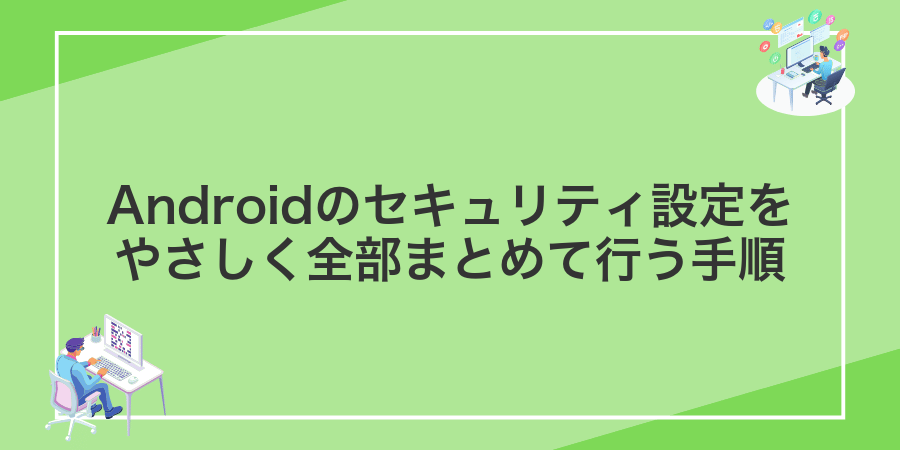
Android14搭載のスマホなら、以下の流れで主要なセキュリティ設定をまとめて整えられます。最初に全体像をサクッと押さえましょう。
- 端末暗号化の確認:設定アプリの「セキュリティ」からストレージ暗号化が有効かチェックする
- 画面ロック設定:PINやパターン、指紋認証を登録して不正なアクセスを防ぐ
- OSアップデート管理:最新のセキュリティパッチを自動で受け取れるよう「システムアップデート」をオンにする
- アプリ権限の見直し:位置情報やカメラなど、不要な権限をオフにしてプライバシーを守る
- Google Playプロテクト:マルウェア検出機能をオンにしてアプリを自動スキャンする
- 不審なWi-Fi対策:公衆ネットワークに接続する際はVPNアプリを起動して通信を暗号化する
エンジニアの経験では、USBデバッグは必要なときだけオンにすると不正アクセスのリスクをグッと抑えられます。
ロック画面をしっかり守る
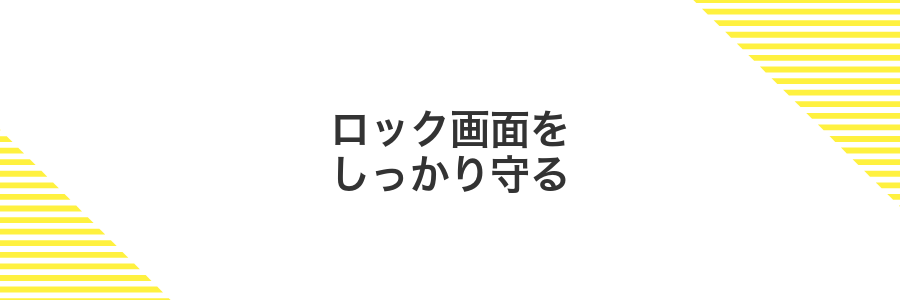
スマホのロック画面は大事なデータを守る最初の壁です。ここがゆるいと大切な連絡や写真が簡単に見られてしまいます。PINやパターン、生体認証を組み合わせるとしっかりガードできますので、自分に合った方法を選んでみましょう。
- 強力なパスコードを設定:数字4桁より6桁以上にすると突破が難しくなります。
- 生体認証を活用:指紋や顔認証を登録するとスムーズにロック解除できます。
- 通知内容を隠す:ロック画面でメッセージの中身を隠す設定にすると情報漏えいを防げます。
①設定アプリを開く
歯車の形をした設定アイコンを見つけたら、やさしくタップしてアプリを開きます。
アイコンの配置は機種によって異なることがあります。見当たらないときはアプリ一覧画面をチェックしてください。
②セキュリティとプライバシーをタップ
設定の一覧を下にスクロールし鍵マークのセキュリティとプライバシーを探しましょう。
見つけたらその部分をタップして設定画面を開きます。
もしリストに見当たらないときは画面上部の検索欄に「セキュリティ」と入力すると表示が絞り込まれます。
注意端末によっては「生体認証とセキュリティ」など設定名が異なる場合があります。
③画面のロックを選ぶ
「設定」の「セキュリティと現在地情報」から「画面ロック」をタップします。端末によっては「セキュリティ」や「ロック画面」と表示が異なる場合がありますので探してください。
- パターン:図形をなぞるだけで手軽ですが、跡が残りやすいので注意が必要です。
- PIN:数字だけなので入力もスムーズですが、推測されにくい組み合わせを選びましょう。
- パスワード:英数字を組み合わせられるので安全性が高いですが、タイプミスに気をつけてください。
パターンを選ぶ場合は汚れや指紋の跡で突破されないよう、定期的に画面を拭いてください。
④PINを4桁以上で決める
数字だけでかんたんに解除できるPINは、最低でも4桁以上にしておくとグッと安全度が上がります。誕生日や“1234”みたいな予測しやすい番号は避けて、覚えやすくて他人には推測されにくい組み合わせを選びましょう。
ホーム画面から歯車アイコンの「設定」をタップします。
「セキュリティと現在地」→「画面ロック」→「PIN」をタップし、4桁以上の数字を入力します。
先ほど入力したPINをもう一度入力して設定を完了させます。
誕生日や連番、同じ数字の組み合わせは予測されやすいので避けましょう。
⑤指紋登録をプラスする
設定アプリを開いて「セキュリティとプライバシー」をタップし、「指紋認証」を選びます。Android13以降では検索窓に「指紋」と入力すると早くたどり着けます。
画面の指示に従って現状のロック解除方法(パターンやPIN)を入力します。もし設定していない場合は、先に画面ロックを登録しておく必要があります。
センサーに指を軽く当て、画面の枠が進むまでゆっくり繰り返します。実際に複数の角度から登録したところ、ロック解除の成功率が格段に上がりました。
登録が終わったら、画面オフから指を当ててみましょう。スムーズにロック解除できれば成功です。
指紋センサーが汚れていると読み取り失敗が増えるため、定期的にやわらかい布で拭いておくと安定感がアップします。
GooglePlayProtectでアプリを見張る

AndroidにはGooglePlayProtectという仕組みがあります。Playストアからインストールされるアプリをバックグラウンドで常にチェックして、不審な動作を見つけるとお知らせしてくれます。
デフォルトで有効になっているか確認しておくだけで、うっかり悪質なアプリを入れてしまうリスクをぐっと減らせます。端末への負荷もほとんどないので、初めての人でも特別な操作なしに安心感が手に入ります。自作アプリをリリース前にテストする際にも、PlayProtectで動作チェックを通しておくと実環境での振る舞いを早めに把握できて便利です。
①Playストアアプリを起動
スマホのホーム画面やアプリ一覧からPlayストアアイコンを探してタップしてください。
もし見つからないときは、画面中央を下にスワイプして表示される検索バーにPlayストアと入力するとすぐに起動できます。
②右上のプロフィールアイコンをタップ
アプリのメイン画面で、右上にある丸いアイコンを探してください。ユーザー名のイニシャルや設定した写真が表示されています。このアイコンをタップするとアカウントメニューが開きます。
機種によってはアイコンがシルエット表示になることがあります。丸いマークを目印にすると迷わずに見つかります。
③PlayProtectを選ぶ
Google Playアプリを開いたら右上のプロフィールアイコンをタップしてください。そのあと「Playプロテクト」を見つけてタップします。
機種やOSによっては「Playプロテクト」表記が「デバイスのセキュリティ」内にまとめられていることがあります。
④スキャンを実行してオンを確認
GooglePlayストアを開いて右上のプロフィールアイコンをタップします。
「Playプロテクト」を選んで「デバイスをスキャン」をタップし、スキャンが完了するまで待ちます。
「保護されています」と表示されれば正常です。そのまま不審なアプリの検出がオンになっていることを確認してください。
スキャン中は他の操作を控えると正確度が上がります。
アプリの権限を見直す
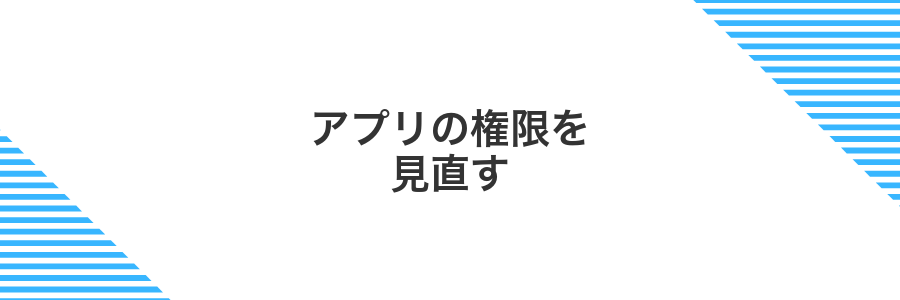
スマホに入っているアプリはいくつかの権限を必要とします。ですが、実際に使っていない機能まで許可したままだと、思わぬ情報が流出したり、バッテリーが早く減ってしまったりします。ここでは、普段あまり意識しないアプリ権限をやさしく見直して、安心感をアップしましょう。
Android13以降では位置情報や通知の権限を細かくコントロールできます。また、一定期間使わなかったアプリは自動で権限をリセットしてくれるので、合わせてチェックすると効果的です。
- 不要な権限を取り消してプライバシーを守る
- 自動リセット機能をオンにして権限の放置を防ぐ
- 使う機能だけに絞ってバッテリー消費を節約
こうしたチェックを週に一度ほどこなすだけで、ぐっと安心度が高まります。まずは気軽にアプリ権限の画面を開いてみてください。
①設定アプリからプライバシーを開く
ホーム画面の歯車アイコンをタップして設定アプリを起動します。機種によってはアプリ一覧から探すこともできます。
設定のリストをスクロールしながらプライバシーを見つけてタップします。ここから各種権限設定を管理できます。
②権限マネージャーを選ぶ
設定アプリを開き、上部の検索バーに「権限マネージャー」と入力します。候補に出てきた「権限マネージャー」をタップすると、カメラやマイクなどの権限一覧画面に移動できます。
この画面で権限をまとめて確認できるので、いつのまにかオンになった権限をオフにしてトラブルを未然に防げます。僕も位置情報の権限が知らずにオンだったのをここで見つけた経験があります。
③各権限をタップして不要アプリをオフ
設定アプリの検索バーに「権限マネージャー」と入力し、起動します。一覧から「カメラ」や「位置情報」など各権限カテゴリが並んでいるのを確認しましょう。
それぞれの権限をタップすると許可済みアプリ一覧が出ます。不要なアプリの横にあるトグルをタップしてオフにしてください。
ひととおりオフにしたら戻るボタンで権限一覧に戻り、位置情報やマイクなど他のカテゴリも同じ手順で整理しましょう。
システムアップデートを忘れずに
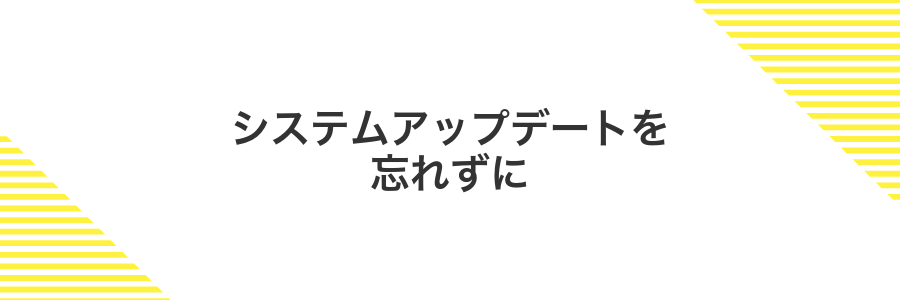
端末が最新のセキュリティパッチを手に入れるのは大切です。Androidでは毎月のシステムアップデートで脆弱性が塞がれるため、放っておくと知らないうちに狙われやすくなってしまいます。
設定アプリから手動でチェックするほか、Wi-Fi接続時に自動でダウンロード・インストールするようにしておくと安心です。夜間や充電中に更新が済むようにしておくと、日中の作業を邪魔されずにすみます。
プログラマー目線のひと工夫としては、リリースノートでどんな脆弱性が直ったかをざっと眺めてみること。自分に関係ありそうな修正内容を知っておくと、万一のトラブル対応がスムーズになることがあります。
①設定アプリでシステムを開く
ホーム画面かアプリ一覧を開いて歯車マークの「設定」をタップします。
設定の一覧をいちばん下までスクロールして「システム」を見つけ、タップして中身を表示します。
端末によっては「一般管理」や「端末情報」と表示されるケースがあります。その場合は同様の位置にあるメニューを選んでください。
②システムアップデートをタップ
設定アプリを開いたら画面を下にスクロールしシステムアップデートを探してください。見つけたらタップしてアップデート画面に進みます。
③更新があればダウンロードして再起動
システム設定の「システムアップデート」画面を開いて、「ダウンロードしてインストール」をタップします。
更新ファイルは数百MB~数GBになる場合があるので、安定したWi-Fiに接続しておくと安心です。
ダウンロードが完了したら「再起動してインストール」を選ぶと、端末が自動で再起動してアップデートが反映されます。
バッテリー残量が20%以下だと途中で停止することがあるため、充電器につないだ状態で実行してください。
Googleアカウントを2段階認証にする
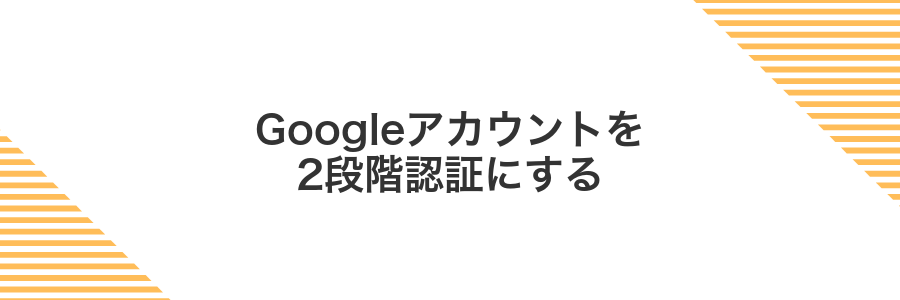
Googleアカウントを2段階認証にすると、パスワードだけではログインできない仕組みになるので安心感がグッと高まります。Android端末からPlayストアやGmailにアクセスするときも、なりすましをしっかりガードできます。
- パスワードだけでは突破できないから不正アクセスを防げる
- SMSや認証アプリでワンタイムコードを受け取れる
- バックアップコードの発行で端末紛失時も復旧がスムーズ
普段からGoogleサービスをたくさん使うなら、ぜひ有効にしておきましょう。認証アプリは「Google Authenticator」以外にも複数選べるので、自分が使いやすいものを選ぶと操作もラクになります。
①ブラウザでmyaccount.google.comを開く
まずはいつも使っているブラウザを開いてみてください。
画面上部のアドレスバーにmyaccount.google.comと入力してエンターキー(または→アイコン)をタップします。
URLを入力すると自動でログイン画面が表示されます。まだログインしていない場合は、Googleアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してください。
②セキュリティを選ぶ
ホーム画面で設定アプリをタップして開きます。
「セキュリティ」または「生体認証とセキュリティ」をスクロールして探し、タップします。
画面内で暗号化や画面ロック、SIMカードのロックなど必要な項目を確認してオンにしましょう。
安全性を高めるために未知のアプリのインストールを禁止に設定しておくと安心です。
端末によって「セキュリティ」「生体認証とセキュリティ」の表記が異なる場合があります。
③2段階認証プロセスを開始
設定アプリを開いて下にスクロールし「Google」をタップしてください。
「Googleアカウントを管理」を選び、上部タブから「セキュリティ」を開きます。
画面内にある「2段階認証プロセス」を探して「開始」をタップしてください。
認証方法はSMSか認証アプリを選べますが、スマホ乗っ取りリスクを避けるなら認証アプリがおすすめです。
認証アプリを選んだ場合、表示されたQRコードをAuthyやGoogle Authenticatorでスキャンしましょう。
最後にバックアップコードを必ずメモして、安全な場所に保管しておくと安心です。
SMS認証はSIM乗っ取りの狙われやすいので、認証アプリを使うとより安全です。
④SMSかGoogleAuthenticatorを設定
2段階認証でアカウントを守るために、SMSかGoogleAuthenticatorのどちらかを選んで設定します。SMSは手軽ですが、アプリを使うとさらに安全に使えます。
Androidの設定から「Google」→「アカウントサービス」→「Googleアカウントを管理」を開いて、セキュリティタブをタップします。
「2段階認証プロセス」をオンにして、SMS(ショートメッセージ)を選択。普段使う電話番号を入力します。
SMSで届いた数字6桁を画面に入力すると設定完了です。以降ログイン時に確認コードが求められます。
Playストアで「GoogleAuthenticator」を検索してインストールします。公式アプリなので安心です。
先ほどのGoogleアカウントのセキュリティ画面で「Authenticatorアプリ」を選び、表示されたQRコードをアプリで読み取ります。
Authenticatorアプリに表示される6桁のコードを画面に入力すれば、設定が完了します。
スマホをなくすとログインできなくなるため、表示されるバックアップコードは必ず紙にメモして安全な場所で保管してください。
端末を無くしたときのFindMyDeviceをオン
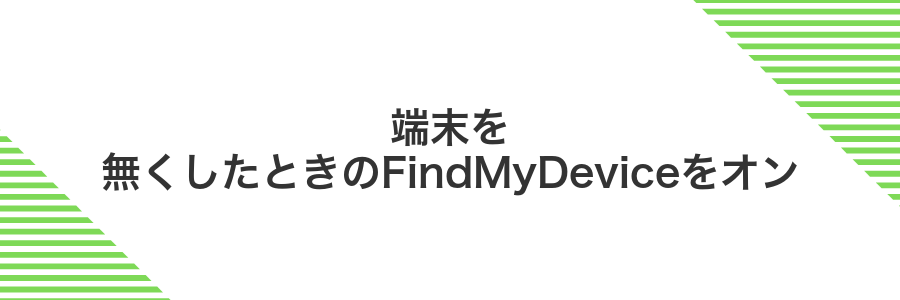
紛失したときに慌てずに端末を見つけ出すには、FindMyDeviceをオンにしておくと安心です。Googleアカウントと連携して、地図で現在地を確認したり、端末から音を鳴らしたり、遠隔でロックや初期化を行ったりできます。
- 地図上で端末の位置をすぐに把握できる
- 見つけやすいように端末から音を鳴らせる
- 遠隔ロックやデータ消去で情報漏えいを防げる
①設定アプリでセキュリティとプライバシーを開く
ホーム画面かアプリ一覧から歯車アイコンの設定アプリを見つけてタップします。
設定画面が表示されたら画面を下にスクロールし、セキュリティとプライバシーという項目を探します。
見つからない場合は画面上部の検索バーに「セキュリティ」と入力すると素早くアクセスできます。
「セキュリティとプライバシー」をタップして、次の設定項目を開きましょう。
②デバイスを探すをタップ
設定アプリの一覧から「Google」を選んだら、表示されたメニューをゆっくり下にスクロールしてデバイスを探すを探します。
見つかったらその項目をタップすると、Googleの「デバイスを探す」設定画面に移動します。
「デバイスを探す」はGoogleアカウントにログイン中でないと表示されません。別アカウントでログインしているときは、同じアカウントでサインインし直してください。
③機能をオンに切り替える
ホーム画面から設定アプリを開きます。
「セキュリティとプライバシー」をタップしてから「Playプロテクト」を選びます。
「デバイスをスキャン」項目のスイッチをタップしてオンに切り替えます。
スイッチの色が変われば完了です。
機内モード中はスキャンが一時停止する点に注意してください。
セキュリティ設定を活かしてもっと安全に楽しむアイデア
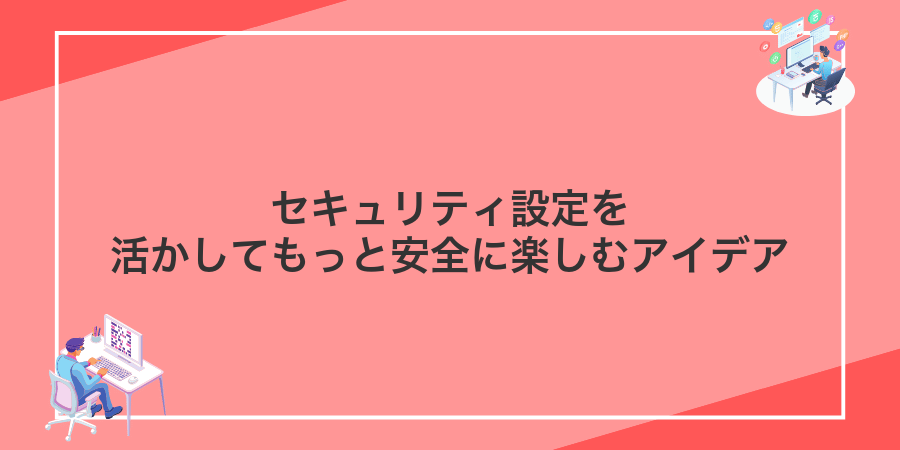
スマホをもっと思いきり楽しみたいなら、セキュリティ設定を使いこなして遊びながら安全を保つテクを試してみましょう。
| 応用アイデア | どう役立つ? |
|---|---|
| 定期的なPlay Protect手動スキャン | 自動検出だけでなく手動でもスキャンして新旧アプリの脅威を見逃さない |
| アプリごとのアクセス権見直し | 不要な権限をオフにして写真や位置情報をしっかりガード |
| VPNを特定Wi-Fiで自動接続 | カフェや公衆Wi-Fiでも通信を暗号化してプライバシーを保つ |
| 安全なDNSプロバイダーに切り替え | 危険サイトや追跡広告をブロックして快適なネット体験 |
| ゲストモード/アカウント切替活用 | 友だちにスマホを貸すときも個人データを見られずに安心 |
| SIM交換時の通知アラート設定 | 不正なSIMロック解除や交換を即キャッチして盗難時も被害を最小化 |
家族の端末をまとめて守る
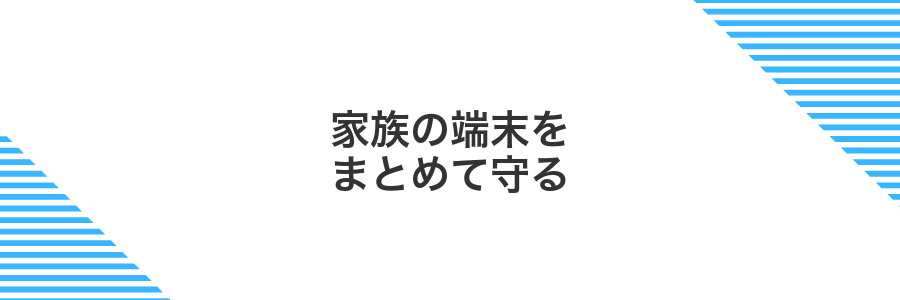
家族の端末をまとめて守るには、Google Family Linkを使った一元管理がラクです。個別に設定するのが面倒でも、これなら誰の端末にも同じセキュリティ対策をパパッと入れられます。
- 統一した保護設定:全端末にPlay Protectや自動OS更新をいっぺんにオンにできる
- 利用制限の一括管理:Family Linkで子どものアプリ利用や時間制限を親のスマホからコントロールできる
- 位置情報の共有:端末の現在地を地図で見られるから、紛失や置き忘れにもすばやく対応できる
- 遠隔ロック・消去:万が一の盗難時も家族全員のデータをすぐに守れる
ファミリーリンクで子ども用Googleアカウントを作成
ファミリーリンクアプリを使って子ども用のGoogleアカウントを安心して登録できます。画面の指示に沿って進めるだけなので、初めてでも迷わず使えます。
親用スマホでGoogle Playストアを開き、ファミリーリンクを検索してインストールします。
アプリを起動して「子ども用アカウントを追加」を選び、画面の案内に従って子どもの名前と生年月日を入力します。
親のGoogleアカウントを使って承認画面にログインし、利用制限やアプリの許可を設定します。
子どもの生年月日を正確に入力すると、年齢に合ったフィルタが自動で適用されます。
共有端末でゲストユーザーを設定
ホーム画面から設定アプリをタップして起動します。虫眼鏡マークを探すより、歯車アイコンを探すほうが早いですよ。
設定内の「ユーザーとアカウント」へ進み、「ユーザー(または複数ユーザー)」を選びます。続いて「ゲストを追加」をタップすると、新しいゲストユーザーが作成されます。
画面上部をスワイプしてユーザーアイコンからゲストをタップします。ゲストモードでアプリを試して、必要なアプリだけ許可するなど設定すると安心です。
公共Wi-Fiでも安心して使うコツ
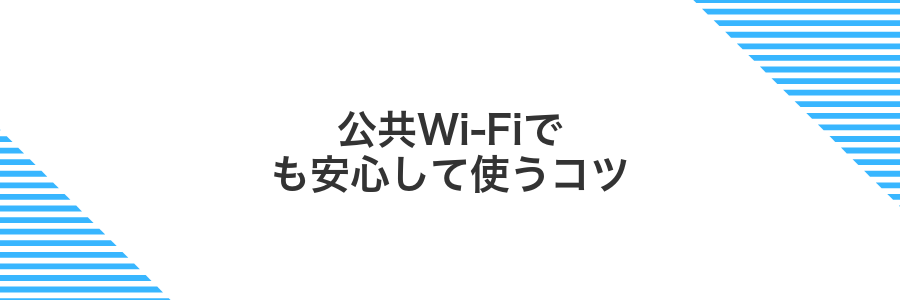
公共Wi-Fiはだれでも気軽につなげる反面、暗号化されていなかったり、中間者攻撃を受けやすかったりします。けれど設定をひと工夫するだけで、心配ごとをグッと減らせます。
まずプライベートDNSを暗号化対応に切り替えると、ドメイン名解決からしっかり守られます。くわえて常時オンVPNを有効にすれば、Wi-Fi接続と同時に自動でトンネリングがかかって安心です。
そのうえで自動接続をオフにしておくと、知らないSSIDに不意につながる心配がなくなり、必要なときだけ手動でWi-Fiを選べます。信頼できるVPNサービスを選べば、駅やカフェのフリーWi-Fiでもストレスフリーにネットを楽しめます。
VPNアプリをインストールして自動接続を設定
Google Playストアを開いて検索欄に「VPN」と入力します。有料無料いろいろありますが、通信速度やセキュリティの評判が良いものを選びましょう。
アプリを開いたら設定メニューへ移動して「自動接続」を有効にします。Wi-Fiやモバイルデータ接続時に自動でVPNが立ち上がります。
公衆Wi-Fi利用時は特に安全性が高まるのでオフにせず運用してください。
Wi-Fi設定で自動接続をオフにする
ホーム画面またはアプリ一覧から設定アイコンをタップします。
「ネットワークとインターネット」を選んでから「Wi-Fi」をタップし、接続済みまたは保存済みのネットワーク一覧を表示します。
対象のSSIDを長押しして「ネットワーク設定を変更」または歯車アイコンを選択し、「自動再接続」や「自動接続」のスイッチをオフにします。
開発者向けオプションをセキュアに試す
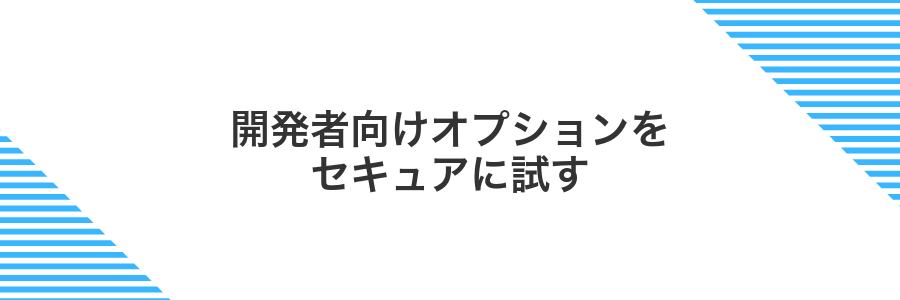
開発者向けオプションは、画面アニメーションの速さを調整したり、USBデバッグで端末とPCを自由にやり取りできたりと、試してみると操作感のカスタマイズがぐっと広がります。
ただし常時オンにすると外部からの不正アクセスリスクが高まるため、テスト用ユーザーを作成して切り替えながら使うと安心です。使い終わったら必ずオプションをオフにするクセをつけると、普段使いの安全性をしっかり守れます。
エンジニア目線のコツとしては、まずはエミュレータ上で動作を試してから実端末へ移行するとトラブルの芽を摘みやすいです。ADB接続は必要なときだけ有効化し、終わったら「USBデバッグを無効化」で未知の通信を防ぎましょう。
USBデバッグを使う前に一時的にオンにする
設定アプリを開き、端末情報に進んでビルド番号を7回タップしてください。タップ回数がカウントされ、完了すると開発者向けオプションが表示されます。
設定画面に戻り、システム→開発者向けオプションをタップします。プログラマー目線でよく使う項目が隠れている場所です。
リストからUSBデバッグを探し、スイッチをタップしてオンにします。接続時に確認ダイアログが出るので、手元のPCを信頼する場合は「OK」を押してください。
USBデバッグを使い終わったら、同じ画面でスイッチをタップしてオフにしてください。作業後は無効にしておくと安全度がアップします。
USBデバッグ中は外部からスマホへアクセスできる状態になるため、終了後は必ずオフにしてください。
作業後はUSBデバッグを必ずオフに戻す
開発用の作業が終わったら、USBデバッグをオフに戻しておくと安心です。そのままにしておくと、パソコンやケーブルを使って勝手に中身を操作されるリスクが高まります。
端末の「設定」をタップして開きます。
「システム」→「開発者向けオプション」を選び、「USBデバッグ」をオフにします。
USBデバッグをオフにしたらケーブルを外す前に必ず画面がロックされることを確認してください。
よくある質問

- Androidのセキュリティ更新が来ない端末でどうすればいいですか?
-
まずは「設定>システム>システムアップデート」で手動チェックしてください。公式サイトからファクトリーイメージを落としてADB経由で更新する手もあります。現場ではキャリアモデルで更新遅延が起きたので、メーカー公式ページの手順でZIPを用意し、
adb sideload update.zipを実行してスムーズに最新パッチを当てました。 - アプリの権限をあとから見直したいときはどうしたらいいですか?
-
設定の「アプリと通知>アプリ情報>権限」でアプリごとにON/OFFを切り替えられます。実務で作業中に写真共有アプリにマイク権限を誤って許可した経験があったので、その場で素早く権限を取り消すと安心です。
- スマホを紛失したときの遠隔ロックやデータ消去はどう設定すればいいですか?
-
「Google Find My Device」を有効にすると遠隔ロックと消去ができます。事前に位置情報とネットワークアクセスを許可しておくことがポイントです。海外出張中に盗まれた際、ブラウザから即座にロック&初期化をかけて大事なデータを守れました。
パターンロックとPINはどちらが安全?
スマホのロック画面で迷うのはパターンロックとPINどちらにしようかという点ですね。どちらも手軽に設定できますが、セキュリティを重視するならPINがおすすめです。
| 認証方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| パターンロック | スワイプだけで直感的に解除できる | 画面の指紋や汚れでパターンがばれることがある |
| PIN | 桁数を増やせば推測が難しくなる | 複雑すぎると忘れやすいのでバランスが大事 |
実際に長い数字を使ったPINにしてからは、不正アクセスの不安がぐっと減りました。覚えやすいけれど推測されにくい組み合わせを選ぶのがコツです。
PlayProtectは常にオンで良いの?
AndroidにはPlayProtectというアプリの安全を見守る仕組みがあります。
大事なのはいつもオンにしておくことです。なぜならバックグラウンドでインストールしたアプリをチェックしてくれて、不審な動きを感じ取るとすぐに教えてくれるからです。
たまに「これは自分で作った安全なアプリだよ」というものを誤って危険視することがありますが、その場合はかんたんに例外登録できます。逆にオフにしたままだと本当に危ないマルウェアを見逃してしまうことがあるので、常にオンが安心です。
2段階認証のバックアップコードはどこに保管する?
2段階認証のバックアップコードは、大切な“もしものとき”に頼りになる存在です。あらかじめ使いやすくて安全な場所にしまっておくと、パスワードを忘れたりスマホを紛失したりしたときにも、スムーズにログインを再開できます。
- 紙に書いて金庫や引き出しにしまう:ネットワークから完全に切り離せるので最も安全です。
- パスワードマネージャーのセキュアノート機能で管理:暗号化された状態でクラウド同期され、複数端末からアクセスできます。
- 暗号化したUSBメモリに保存:オフラインで持ち運べるうえ、書き換え禁止設定も可能です。
- 信頼できる家族や友人に預ける:緊急時に頼める相手がいると安心です。
エンジニアからのひとこと:クラウド型ストレージにプレーンテキストで保存すると、アカウント乗っ取りリスクが高まります。必ず暗号化かオフライン管理を組み合わせてください。
開発者向けオプションをオンにすると危険?
スマホの隠し設定である開発者向けオプションを有効にすると、普段は見えない端末の細かい設定をいじれるようになります。
デバッグのために便利な反面、知らないうちにセキュリティの穴を広げてしまうこともあるので、必要なときだけ切り替えるのが安心です。
- USBデバッグを通じて不正アクセスを受けやすくなる
- ログに機密情報が残りやすく、詐欺アプリに悪用される
- アプリの動作を強制的に変更すると正常動作が崩れることがある
実際に仕事で何度かUSBデバッグのまま放置してしまい、知らないうちにファイルを抜かれたことがあります。設定をいじるときは使ったらすぐオフにするクセをつけるとトラブルを防げます。
セキュリティアプリは追加で入れるべき?
Androidには標準機能でのウイルス検知や不正アプリ防止、定期的なセキュリティパッチ配信が用意されているので、いつもの使い方なら追加アプリがなくても十分安心できる経験があります。
とはいえ、公衆Wi-Fiでの作業が多かったり、知らないAPKをよく試すなら専用のセキュリティアプリを1本加えると不安がぐっと減ります。
追加アプリは動作に影響することもあるので、自分の使い方に合った機能だけを選ぶのがおすすめです。
まとめ

Androidのセキュリティは、画面ロック設定→OS&アプリ更新→PlayProtect有効化→不要権限の見直し→定期バックアップ→2段階認証導入→重要データの保護と進めると安心です。
さあ、ひととおり準備が整ったら、あとは安心してAndroidを使いこなすだけです。毎日のスマホライフをもっと楽しく快適にしましょう。